

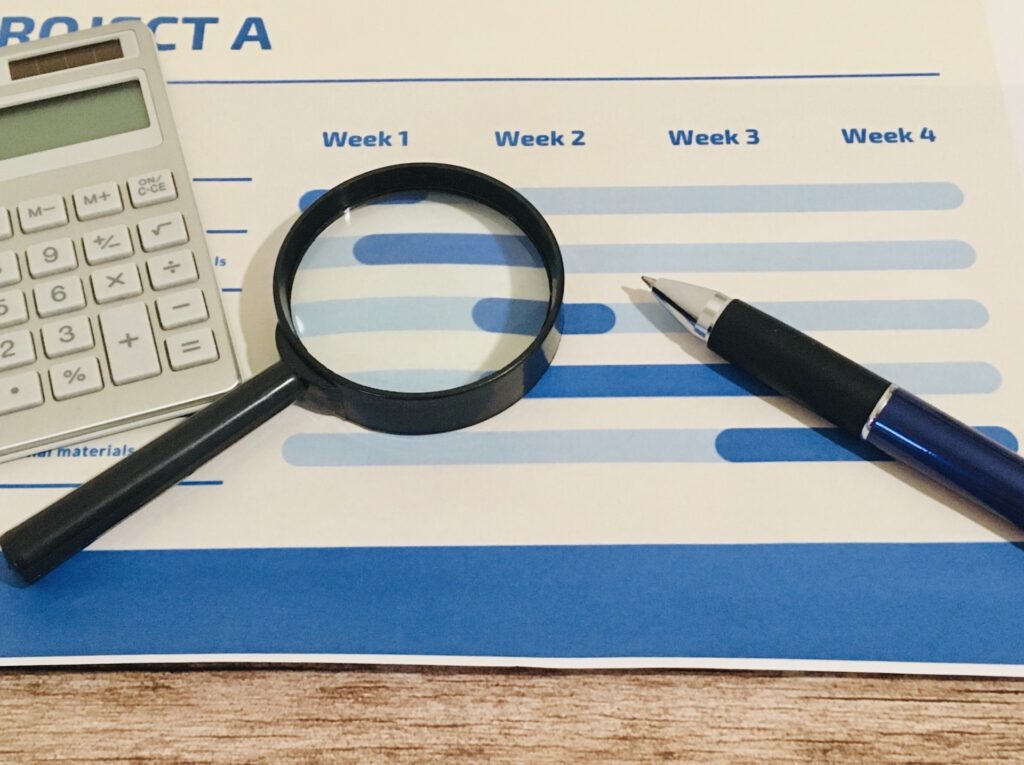
「余裕を持ったスケジュールを立てたはずなのに、なぜか遅れる」──そんな経験はありませんか?実は、プロジェクトがうまくいかない原因は、“余裕”の持ち方そのものにあるかもしれません。従来の計画重視のマネジメントに代わり、実行力と進捗の見える化に重点を置く手法として注目されているのがCCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)です。本記事では、プロジェクトの“遅れの本質”に迫りながら、CCPMの基本と導入のポイントを解説します。
プロジェクトを遅延させないために“余裕を持ったスケジュール”を組むのは、常識的な対策に思えるかもしれません。しかし、実際には「余裕を入れたのに間に合わない」という事態が頻発しています。これは、「学生症候群(着手が遅れる)」「パーキンソンの法則(作業は与えられた時間を使い切る)」といった人間の心理的傾向が影響しているからです。個別に余裕を持たせると、誰もが“自分の都合”でそれを使い切る結果となり、結果的にプロジェクト全体の遅延を引き起こしてしまいます。
CCPM(Critical Chain Project Management)は、従来のWBS(作業分解構造)型のPMとは異なり、実行と流れの最適化を重視するプロジェクトマネジメント手法です。TOC(制約理論)をベースに、「プロジェクトのどこが一番遅れやすいか=制約(クリティカルチェーン)」を特定し、その制約にリソースを集中させるのが特徴です。タスクごとに余裕を入れるのではなく、プロジェクト終盤に“統合バッファ”を置くことで、全体進行のリスクを一箇所でマネジメントします。これにより、チームは無駄のない流れで動きやすくなります。
CCPMでは、各タスクに“余裕”を分散して設定するのではなく、最も遅延リスクの高い一連の流れ(=クリティカルチェーン)を特定し、そこに一括してバッファを配置します。これにより、遅延が起きてもどのくらい“バッファを食っているか”で判断ができるようになるため、プロジェクトマネージャーはタイムリーに対処できます。この仕組みによって、「予定より早く終わったのに報告しない」「手待ちが発生する」などの非効率が減り、チーム全体が前向きに進行を維持できるようになります。
従来のPMでは、進捗確認はタスクごとの完了報告に依存していましたが、CCPMではプロジェクト全体のバッファ消費率をもとに進捗を判断します。この“共通の物差し”により、プロジェクトの現状が視覚的に共有され、リーダーの判断もスピードアップできます。また、遅れている人を責めるのではなく、「どこでリカバリーするか?」という建設的な対話が生まれやすくなる利点もあります。CCPMは単なる管理手法ではなく、チームの意思決定の質そのものを変えるフレームでもあるのです。
CCPMを導入することで、納期遵守率の改善、意思決定の迅速化、チームの心理的安全性向上というように、多面的な効果が期待できます。特に、複数案件を同時に走らせる企業や、納期が厳しいプロジェクトが多い業界では、その威力を発揮します。
ただし注意点もあります。タスクごとの見積もり精度が低いままだと、バッファ管理がうまく機能しません。また、進捗報告のあり方や“先に終わったらすぐ報告する”文化への転換も求められます。仕組みの導入だけでなく、組織の意識改革とセットで考えるようにしましょう。
本記事では、CCPMの基本的な考え方と、“余裕”がプロジェクトに与える影響を解説しました。個別の余裕ではなく、全体最適のバッファ管理こそがプロジェクト成功のカギ。CCPMは、単なる進捗管理を超え、組織の“実行力”を引き出す考え方でもあります。失敗を減らし、納期を守るチームをつくるために、今こそCCPMを見直してみてはいかがでしょうか。
副業をお考えのみなさんへ
ご覧いただいている「月刊タレンタル」を運営するtalental(タレンタル)株式会社では、BizDev領域の即戦力人材レンタルサービス「talental」を提供しています。
現在、副業・フリーランス人材のみなさんのご登録(タレント登録)を受け付けています。タレント登録(無料)はこちらから。
これまで培ったスキルやノウハウを活かして、さまざまな企業のプロジェクトに参画してみませんか?