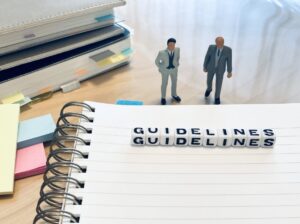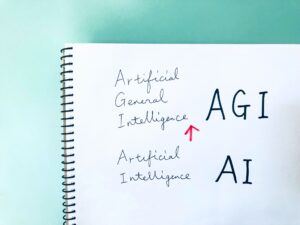ウェブアクセシビリティは、全てのユーザーがウェブサイトを問題なく利用できるようにするための重要な概念です。本記事では、ウェブサイト担当者が知っておくべき基本的なウェブアクセシビリティの知識と、その実践方法について詳しく解説します。アクセシビリティを向上させることで、より多くのユーザーにリーチできるだけでなく、法律遵守やブランドイメージの向上にもつながります。
ウェブアクセシビリティとは、障害の有無や年齢、使用環境にかかわらず、全ての人がウェブサイトの情報にアクセスできるようにすることを指します。例えば、視覚障害のある人がスクリーンリーダーを使用してウェブページを読み上げさせることや、色覚障害のある人が特定の色の区別がつかなくても情報を理解できるようにすることなどが含まれます。
ウェブアクセシビリティの重要性は、多くの理由から高まっています。まず、法律の観点から、2024年4月1日から施行された改正障害者差別解消法により、事業者は障害者への合理的配慮が義務化されました。さらに、高齢者人口の増加に伴い、加齢による視力や聴力の低下を考慮したウェブサイトの設計が求められています。これにより、より多くのユーザーがウェブサイトを利用できるようになるため、アクセス数やユーザー満足度の向上にもつながります。
ウェブアクセシビリティを実現するためには、具体的なガイドラインに従う必要があります。最も代表的なものは、WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)です。これらのガイドラインでは、認知しやすさ、操作しやすさ、理解しやすさ、堅牢性という4つの原則に基づいて、ウェブコンテンツがどのように設計されるべきかが詳細に説明されています。また、日本国内ではJIS X 8341-3:2016という規格も存在し、これに準拠することで国内の法律にも対応できます。

ウェブアクセシビリティを実践するためには、以下のステップを踏むことが重要です。
ウェブアクセシビリティの向上は、様々な効果をもたらします。まず、障害者や高齢者を含む多様なユーザーがウェブサイトを利用しやすくなるため、アクセス数が期待できます。また、アクセシビリティを考慮したデザインは一般ユーザーにとっても使いやすいものとなり、ユーザーエクスペリエンスが向上します。さらに、法律遵守によるリスク回避や、社会的責任を果たすことでブランドイメージの向上にも寄与します。
具体例として、デジタル庁のガイドブックで紹介されている以下の取り組みを挙げます。
視覚障害者がウェブページを利用できるように、スクリーンリーダーで読み上げられるテキストを提供することが重要です。例えば、画像には必ず代替テキスト(altテキスト)を設定し、リンクには明確な説明を付けることで、視覚に頼らずともコンテンツを理解できるようにします。
障害者がマウスを使わずにキーボードだけでウェブサイトを操作できるようにすることが求められます。すべての機能にキーボードショートカットを設けたり、タブキーを使ってリンクやフォームフィールド間を移動できるようにすることが含まれます。
色覚特性があるユーザーが情報を正確に理解できるように、色のコントラスト比を適切に設定することが大切です。例えば、重要な情報を色だけで伝えるのではなく、形やテキストを使って補完することで、色覚特性があるユーザーにも対応します。
聴覚障害者が音声コンテンツを理解できるように、動画には字幕を付けたり、手話通訳を提供することが推奨されます。これにより、音声情報が聞こえない場合でも内容を理解できるようになります。
この記事では、ウェブアクセシビリティの基本的な概念とその重要性、具体的なガイドラインや実践方法について解説しました。ウェブアクセシビリティを向上させることで、多様なユーザーが利用しやすいウェブサイトを実現でき、アクセス数の増加やユーザーエクスペリエンスの向上、法律遵守やブランドイメージの向上といった効果が期待できます。これからウェブサイトを改善しようとする担当者にとって、本記事が役立つことを願っています。
副業をお考えのみなさんへ
ご覧いただいている「月刊タレンタル」を運営するtalental(タレンタル)株式会社では、BizDev領域の即戦力人材レンタルサービス「talental」を提供しています。
現在、副業・フリーランス人材のみなさんのご登録(タレント登録)を受け付けています。タレント登録(無料)はこちらから。
これまで培ったスキルやノウハウを活かして、さまざまな企業のプロジェクトに参画してみませんか?