

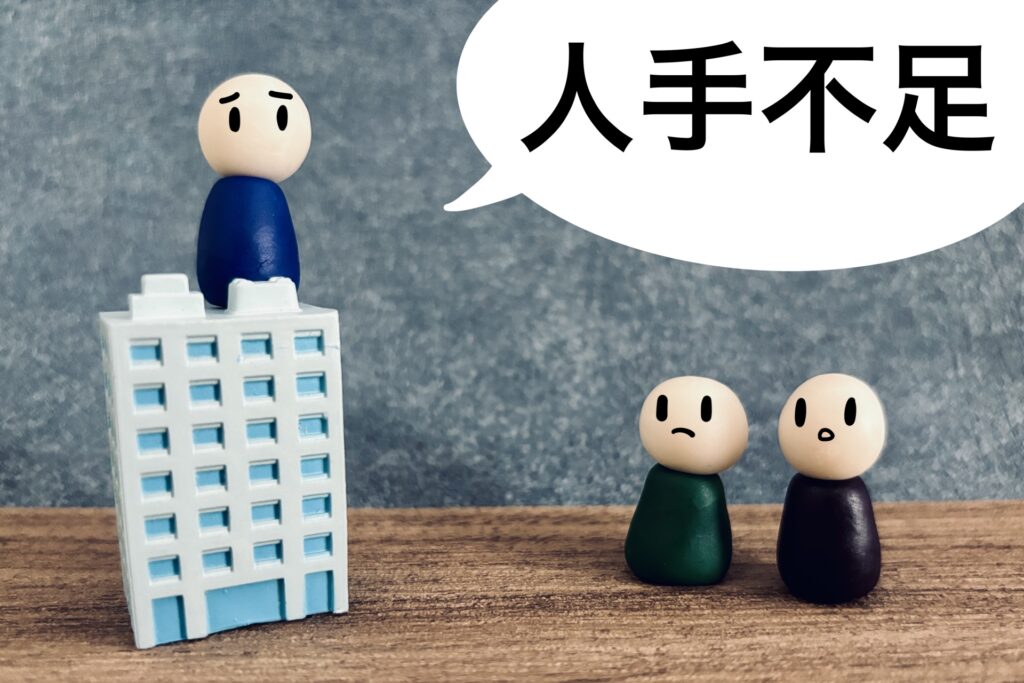
少子高齢化が進む日本では、生産年齢人口の減少は避けられない現実で「労働供給制約」が起こりがちです。人手不足の時代を単なる逆境と捉えるだけでは事業の成長は止まってしまいます。本記事では、この大きな変化を「事業成長の新たな機会」として捉え直しどのように立ち向かうべきか、その具体的な戦略と思考法を解説します。
働供給制約とは、企業が求める労働力に対して、実際に働くことを希望する人(労働供給)が不足している状態を指します。多くの人が「労働供給制約=人手不足」と考えがちですが、この問題はもう少し複雑です。単に絶対的な労働人口が減っているだけでなく、以下のような複数の要因が絡み合って、従来の雇用モデルが機能しなくなっている状態を指します。
これは最も根本的な要因です。日本では、生産年齢人口(15〜64歳)が年々減少しており、労働力の絶対数が減少し続けています。また、高齢者や女性の社会進出は進んでいるものの、フルタイム勤務や特定の専門職を希望する人が減り、働き方の多様化が進んでいます。これにより、企業が求める人材と、市場にいる人材との間にミスマッチが生じやすくなっているのです。
現代の労働者は、仕事だけでなくプライベートも大切にしたいと考える人が増えています。長時間労働を前提とした働き方や、旧態依然とした企業文化は敬遠されがちです。また、終身雇用が当たり前ではない時代になり、多くの人がスキルアップやキャリアチェンジを目的とした転職に前向きです。企業は、ただ採用するだけでなく、働きがいや柔軟な働き方を提供し、人材をつなぎとめる努力が不可欠になっています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展に伴い、AIやデータサイエンス、サイバーセキュリティなどのデジタル人材の需要が急増しています。しかし、これらのスキルを持った人材の育成・供給が追いついておらず、激しい争奪戦が繰り広げられています。これにより、特定のスキルを持った人材が特定の業界に偏在し、人材不足がさらに深刻化しているのです。
我々がまずやるべきことは、自社が直面している「労働供給制約」が、これらのどの要因によって引き起こされているのかを深く掘り下げ、課題の根本を見極めることです。それが、有効な打ち手を考えるための第一歩となります。
労働供給制約が深刻化する今、外部から優秀な人材を「獲得」する競争は激化する一方です。これからは、社内外問わず、すでに存在しているリソースをいかに効率的に「活用」するかに焦点を当てるべきです。具体的には、既存社員のスキルアップやリスキリングを積極的に支援することで、一人ひとりの生産性を高めることが重要です。新しいスキルを習得した社員が、これまでとは違う業務に挑戦することで、組織全体の新たな活路が開ける可能性もあります。
さらに、フリーランスや副業人材、業務委託といった外部のパートナーを戦略的に活用することも不可欠です。必要なスキルや専門知識を必要な期間だけ外部から調達することで、採用コストを抑えつつ、事業のスピードを維持することができます。この場合、単なる一時的な戦力としてではなく、戦略的なビジネスパートナーとして捉え、長期的な関係性を築くことが重要です。
労働供給制約という課題を前に、テクノロジーの活用は避けて通れません。例えば、これまで手作業で行っていたデータ入力や分析、顧客とのコミュニケーションといった定型業務を、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などのツールで自動化することで、社員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。これにより、限られた人材でも事業を拡大していくことが可能になります。
また、営業活動においても、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)ツールを導入することで、顧客情報の共有や営業プロセスの可視化が進み、属人化を排除することができます。チーム全体で情報を共有し、効率的に連携することで、少ない人数でも大きな成果を上げられる組織へと変革できるのです。テクノロジーは単なる効率化のツールではなく、人手不足を乗り越えるための強力な武器となります。
従来の採用チャネル(新卒採用、中途採用)だけでは、労働供給制約に対応するのは難しいのが現状です。これからは、既存の枠組みにとらわれない、新しい採用・育成のチャネルを積極的に開拓していく必要があります。
例えば、育児や介護などで一時的にキャリアを離れている潜在的な労働力にアプローチする再就職支援プログラムを立ち上げたり、専門スキルを持った副業人材とのマッチングサービスを活用したりすることも有効です。また、自社の事業内容や働き方の魅力を積極的に発信することで、リファラル採用を強化するのも効果的です。社員からの紹介であれば、企業文化にフィットする人材を効率的に獲得できる可能性が高まります。
育成面では、社内のメンター制度やeラーニングの導入により、社員の自己成長を促す仕組みを整備することが重要ですです。社員一人ひとりが自律的にスキルアップできる環境を提供することで、定着率が向上し、結果として人材流出を防ぐことにもつながります。新しいチャネルを開発することは、採用コストの削減にも貢献します。
最後に、最も重要なのが「組織文化のアップデート」です。人手不足が深刻化する時代においては、社員が「この会社で働き続けたい」と思えるような魅力的な組織をつくることが、事業を継続的に成長させるための基盤となります。具体的には、心理的安全性の高いチームづくりが挙げられます。社員が自分の意見やアイデアを自由に発言でき、失敗を恐れずに挑戦できる環境を整えることで、イノベーションが生まれやすくなります。
また、社員のワークライフバランスを尊重し、柔軟な働き方を認める文化を醸成することも重要です。リモートワークやフレックスタイム制、育児休暇の取得促進など、個々のライフスタイルに合わせた働き方を認めることで、社員のエンゲージメントが高まり、結果として生産性の向上にもつながります。社員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることが、労働供給制約を乗り越える最大の鍵となるでしょう。
本記事では、労働供給制約を単なる課題ではなく、事業成長の機会として捉えるための5つの戦略的思考法について解説しました。人手不足という現実を前に、まずはその本質を理解し、人材を「獲得」から「活用」へ、業務を「属人化」から「標準化」へとシフトしていくことが不可欠です。
そして、テクノロジーを活用した業務改革、新たな採用・育成チャネルの開発、そして最も重要な組織文化のアップデートを通じて、限られたリソースでも最大限の成果を出せる強い組織へと変革していくことが求められます。これらの視点を持ち、能動的に事業を推進していくことが自社の未来を切り拓く鍵となるでしょう。
副業をお考えのみなさんへ
ご覧いただいている「月刊タレンタル」を運営するtalental(タレンタル)株式会社では、BizDev領域の即戦力人材レンタルサービス「talental」を提供しています。
現在、副業・フリーランス人材のみなさんのご登録(タレント登録)を受け付けています。タレント登録(無料)はこちらから。
これまで培ったスキルやノウハウを活かして、さまざまな企業のプロジェクトに参画してみませんか?







